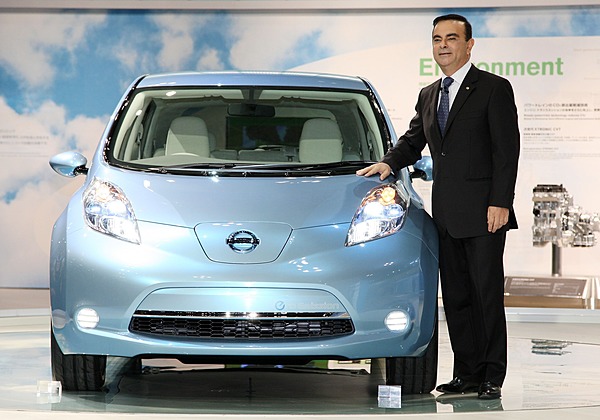【マツダを救いたい】マツダが電動化戦略を大幅改定! でもマツダのEVをオススメしません
マツダが2030年までの電動化戦略を大幅に更新し、特に2025年までに完全な電気自動車を3車種も市場に投入し、2030年までの電動化率100%達成という大方針も発表してきましたが、
それと同時に、そのマツダの電動化プランをはじめとする将来性に対して、大きな懸念も存在することについて徹底的に解説します。
日本メーカー5番手&電動化で出遅れ中
まず、今回のマツダに関してですが、日本を代表とする自動車メーカーの1つとなっていて、
新型コロナウイルスによるパンデミックの影響を受ける前の、2019年度における自動車の販売台数は、グローバルで150万台弱と15位という位置につけ、
それより上には、現在急成長中のインド市場において成功を収めているスズキと、日本メーカービッグ3である、ホンダ、日産、そしてトヨタという巨大自動車メーカーしか存在していませんので、
並み居る強豪がひしめき合う日本国内で見ても、そしてグローバルで見ても、一定のシェアを確立しているのですが、

電気自動車という観点においては、世界の流れに完全に乗り遅れてしまっている状況となっていて、グローバルにおいては、昨年になるまで電気自動車を発売することはなかったのですが、
その昨年である2020年の8月から、ついにマツダ初の量産電気自動車であるMX-30をヨーロッパ市場において発売し、
特に2020年末付近の販売台数については、その電気自動車先進諸国の集結するヨーロッパ諸国の一部の国において、人気車種ランキングトップ20にもランクインしてくるという、
個人的には想定以上の販売台数を達成することができていたのです。

しかしながらその後に関しては、そのランキングからは名前を消し、
その電気自動車需要が急増中のヨーロッパ市場だけでなく、我々日本市場における販売台数に関しても、圧倒的低水準に留まってしまっているということで、
先行して発売がスタートしていたヨーロッパ市場から少し遅れて、今年である2021年に入ってから納車をスタートさせているMX-30の日本市場における販売台数は、
1月度こそ、97台という販売台数を記録してはいますが、その後は、29台、12台、6台、そして直近である5月度の販売台数についても、9台という、
その生産体制や物流体制に、何か問題が発生しているとしか思えないほどの不人気ぶりであるのです。

ただし、マツダに関しては、今回のMX-30の日本国内の年間販売台数目標を500台、
つまり、月間で40台程度という、そもそも圧倒的低水準な目標を設定していますので、
特に販売初月であった1月度の97台が爆売れし過ぎてしまったため、現在は月間10台弱にセーブしている、という感じでしょうか?
EVとしての質は2021年最低レベルという事実
そして、こちらのMX-30に関しては、以前の動画でも複数回にわたって解説している通り、その電気自動車としての質が極めて低いということで、
そもそも論として、本チャンネルにおけるその判断基準である、満充電あたりの航続距離や充電性能というのは、2021年に発売されている電気自動車としては、最低水準であり、
例えば満充電あたりの航続距離については、高速道路を時速100kmでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値するEPAサイクルにおいて、
概算値とはなりますが、178km程度に留まってしまい、さらに、その最大充電出力に関しても、最大50kWと、
11年前に発売されている、初代日産リーフと同程度のスペックに留まってしまっているのです。
そして、さらに悪いことというのが、このマツダ側がアナウンスしているスペックを、実際の第三者機関による検証において、軒並み達成することができていないという点であり、
特にその充電性能に関しては、マツダ側が主張している50kWという数値には遠く及ばず、最大でも37kW程度までしか達していないことが判明し、
こちらに関しては複数の検証においても同様の結果となってしまいましたので、
特に今回のMX-30において強調されていた、搭載されているバッテリーパックに強制水冷機構というバッテリー温度管理機構が搭載されていることによって、
質の高い充電性能を達成することのできるという主張とは、明らかに相反しているということが、図らずも浮き彫りとなってしまっているのです。

2018年まではEV時代は訪れないと予測
このようにして、すでに電気自動車を発売してはいるマツダについては、その中身を正確に読み解いていくと、
やはり電気自動車開発であったり、その生産台数の明らかな制限から透けて見える、搭載バッテリーの調達の難航という点において、
明らかに競合メーカーと比較して後塵を拝してしまっている感が否めないのですが、
そのような現状において、今回新たに明らかになってきたことというのが、そのマツダが今後の電動化戦略を大幅に見直してきたということで、
そもそも今までの電動化戦略に関してですが、2018年度において発表されていた”Sustainable Zoom Zoom 2030”という長期経営戦略に則った方針となっていて、
特に電気自動車という観点においては、2030年までにグローバルで発売する全ての車両を電動化するという方針を示していたのです。

しかしながら、この電動化という表現は最も注意しなければならない表現方法となっていて、
そもそも日本市場における電動車の定義というのは、本チャンネルにおいて取り上げている、
搭載された大容量のバッテリーに充電して貯められた電力のみを用いて走行する、完全な電気自動車を始め、
そのバッテリーの他に、既存のガソリンエンジンも搭載して両方を併用して走行することができるプラグインハイブリッド車の他にも、
日本メーカーが得意としている、通常のハイブリッド車も、その電動車の定義の中に含まれてしまっている、
つまり、ガソリンを使用することでしか走行することができないという意味において、既存のガソリン車やディーゼル車となんら変わらないハイブリッド車についても、
今回のマツダの電動化戦略に含まれているということになるわけなのです。

また、その電動車100%の内、完全な電気自動車の販売目標割合は、なんとたったの5%と、
したがって3年前である2018年度においては、マツダは2030年になっても電気自動車の時代は訪れることはない、
よってその販売台数も相当なニッチ分野になるであろうと考えていた、ということなのです。
たった3年間でEV販売台数目標を5倍に
そして、今回の2021年度において新たに発表された電動化のタイムラインについてですが、
もちろん今までの、2030年までの電動車100%という目標設定については特に変更がないものの、
最も特筆すべきは、そのうちの完全な電気自動車の販売目標割合を、大幅に上方修正してきているという点であり、
その割合が、25%と、なんと3年前に発表してきていた5%という割合の、なんと5倍、
つまり、たったの3年間というタイムスパンにおいて、マツダは10年後に発売している完全な電気自動車の販売台数を、5倍にまで高めてきた、ということなのです。

さらにマツダに関しては、「SKYACTIV Multi-Solution Scalable Architecture」と名付けられた、
ハイブリッド車からプラグインハイブリッド車、そして、完全な電気自動車と、全ての車種に対応可能な共通のプラットフォームを開発し、
来年である2022年から2025年までの3年間の間に、なんと合計して13車種もの電動車にその共通プラットフォームを採用し、
主要マーケットである北米市場や、ヨーロッパ、中国、そして我々日本市場において投入する予定となっています。
ちなみに、その13車種の電動車の内訳についてですが、
5車種がハイブリッド車、さらに5車種がプラグインハイブリッド車、そして3車種が完全電気自動車ということになりますので、
つまり、来年である2022年から概ね1年おきに、マツダから完全な電気自動車が発売されていくとイメージしてみれば、
今までの完全電気自動車に及び腰であったマツダとは思えないほどの、かなりアグレッシブなタイムラインであるとも捉えることができるとは思います。

ただし注意しなければならない点というのは、この「SKYACTIV Multi-Solution Scalable Architecture」というプラットフォームは、
あくまでも既存の内燃機関車であるハイブリッド車も内包した、共通のプラットフォームであり、電気自動車専用プラットフォームではないという点であり、
つまり、すでに発売され、その電気自動車としての質が、競合車種と比較してもかなり劣ってしまっていたMX-30と全く同様に、
内燃機関車と共通のプラットフォームを採用することによって、その電気自動車としての質を妥協してしまう可能性が考えられますので、
早ければおそらく来年である2022年中にも発売がスタートするであろう、マツダの新型電気自動車の質、
特にその充電性能をどれほど改善することができているのかにも、注目していかなければならないとは感じます。

しかしながら、今回のマツダに関してはこれでは留まらずに、
その「SKYACTIV Multi-Solution Scalable Architecture」を採用した電気自動車の3車種を発売した後については、
いよいよ電気自動車専用プラットフォームを採用した、いわば本気の電気自動車も市場に展開していくことを表明してきたということで、
それが、「SKYACTIV EV Scalable Architecture」と呼ばれるプラットフォームであり、
この電気自動車専用プラットフォームを採用し、2025年にも、新型電気自動車に搭載して発売をスタートさせる方針も示してきていますので、
やはり共通プラットフォームでは、よりバリエーションに富んだ車格や、ボディタイプに対応することが難しいということ、
そして、やはり電気自動車専用プラットフォームを採用しないことには、競合車種と比較して、真に競争力のある電気自動車は作れないという考えが透けて見えてくるのではないでしょうか?

”人間中心”の自動運転ってなんすか?
ここまでは、今までガソリンエンジンやディーゼルエンジンという内燃機関車にこだわりをもって開発に取り組んできたマツダが、
ついに電動化に舵を切り始めたという動きについてを解説してきましたが、
それとともに、今回のマツダの電動化戦略をはじめとして、大きく懸念しなければならない点も存在し、
まず電動化という点からは外れるのですが、
この電動化という自動車業界を襲っている津波の第一波よりもさらに巨大な第二波の、自動運転という大津波について、
マツダ側は、「Mazda Co-Pilot Concept」と呼ばれる、自動運転技術を発表し、
こちらは、いわゆる世界の自動車業界だけではなく、テック企業も目指している完全な自動運転というものではなく、
例えば、車が常に運転可能な状態でスタンバイし、万が一のミスや運転継続が困難と判断した場合に、車側がオーバーライドし、周囲を含め安全な状態を確保するといった、
人間中心の自動運転技術を目指しているとしていて、
もちろん過渡期的な意味においては、このような人間の運転を補佐するような自動運転技術に対しても一定の需要が存在するとは考えられますが、

果たして自動運転、特に一定の条件下における完全自動運転を達成することができるレベル4自動運転以降が開発されてしまった場合、
そのマツダの人間中心の自動運転機能を、人は求めるのか、非常に疑問を感じますし、
2021年現時点において、人間中心の自動運転というようなビジョンは、かなり前時代的な印象しか感じないのは私だけでしょうか?
マツダさん、この論文大丈夫っすか?マジで。
そしてマツダに関しては、以前の論文において、
大容量のバッテリーサイズを搭載している電気自動車より、マツダの発売しているディーゼル車の方が、ライフサイクルで見たCO2排出量が少なくなるとの試算を出し、
この論文を引用して、日本中で電気自動車懐疑論が飛び交っていますが、
その前提となっている数値は、明らかに2021年に発売されている電気自動車においては当てはまらない数値であり、
特にわかりやすいポイントとして、その搭載されている大容量のリチウムイオンバッテリーを、16万km走行した段階で交換しなければならないという前提条件についてですが、

こちらはすでに強制水冷機構によって、バッテリー温度を最適に管理することのできるテスラ車のバッテリー劣化率から、
おおよそ25万km走行した後でも、そのバッテリー劣化率は8%、
つまり、バッテリー交換など気にする必要がない程度の劣化率に止めることができていますので、
今だに電気自動車のバッテリーはすぐに劣化するから、16万km走行した後はバッテリー交換を行わなければならないという情報を発信し、
そして現在のこの日本市場における質の低い電気自動車懐疑論の土壌を形成してしまった、このマツダの罪は、非常に重いと言わざるを得ません。

もちろんですが、この論文を今だに撤回していないということは、
自身が発売している電気自動車、つまりMX-30についても同様に当てはまるということ、
要するに、現在発売されているMX-30における、そのマツダがアピールしている、温度管理機構によってバッテリー劣化を抑えることができるバッテリーパックというのは、
16万km走行後に交換しなければならないことになりますので、
大変残念ながら、そのような質の低い電気自動車を、2021年現時点で購入を勧めることは絶対にできませんし、
逆に、御社の電気自動車は16万km走行した後に、何十万円もかけてなぜバッテリー交換をしなければならないのか、
強制水冷機構を搭載しているのにも関わらず、それだけバッテリー劣化が進行してしまうような、考えられないような電気自動車をなぜ普通に販売することができるのか、
こちらは是非ともマツダの開発側に詳しく話を聞いてみたいものです。

電動化推進の前に、やることありませんか?
何れにしてもこのように、内燃機関車に注力し続けてきたマツダに関しても、ついに電動化時代に対応するために、特に新型電気自動車を今後矢継ぎ早に投入する計画を明らかにしてきましたが、
やはりその電気自動車としての質は、電気自動車専用プラットフォームを採用しないことによって、当面は期待することができないという点、
さらには、マツダのあまりにも現実離れした前提条件を元に算出された、電気自動車はエコではない理論というのは、
現在120%の確率で誤った電気自動車懐疑論を拡散し、日本市場の電動化の足を引っ張っているという点、
そして、この論文を今だに撤回していないということは、
マツダが発売している電気自動車であるMX-30は、16万km走行した後にバッテリー交換が待ち受けていることになりますので、
電気自動車専門チャンネルとして、その購入は絶対にオススメすることはできませんし、
そして今後発売してくる新型電気自動車においても、全く同様に、競合車種ではほぼあり得ないレベルのバッテリーのへたり具合となり、その購入はオススメできませんので、

おそらくマツダ側もわかっているとは思いますが、
早くその明らかに前時代的な電気自動車に対する知識をアップデートし、すぐにでもこの論文を撤回、そしてアップデートすることが、
将来の電動化戦略などを発表する前に、現在のマツダが取り組まなければならない、最も重要な課題なのではないでしょうか?
From: Mazda
Author: EVネイティブ