【充電インフラ競争完全敗北】アメリカがEV用急速充電器を80km間隔で大量設置を決定
アメリカの連邦政府が、アメリカ全土を走っているハイウェイ上の80km間隔に、
最低でも150kW級という超急速充電器を4台以上設置していく方針を表明しました。
アメリカがEV用急速充電インフラに大規模投資を表明
まず、今回の方針に関してですが、アメリカのバイデン政権下において可決した、
超党派インフラ投資法案、いわゆるBILの一環として、
すでにバイデン大統領が直々に、電気自動車用の充電インフラを大陸全土に普及させる方針を示していたわけですが、
ついに今回、その全国的な急速充電ネットワーク構築の第一歩として、
アメリカのエネルギー省と運輸省が合同で立ち上げた事務所が、大陸全土に急速充電器を設置する施策、
特にどのようなスペックを持つ急速充電器を設置するのか、
どのような設置要綱を守れば、連邦政府からの補助金を申請することができるのかなどという詳細を、発表してきたのです。
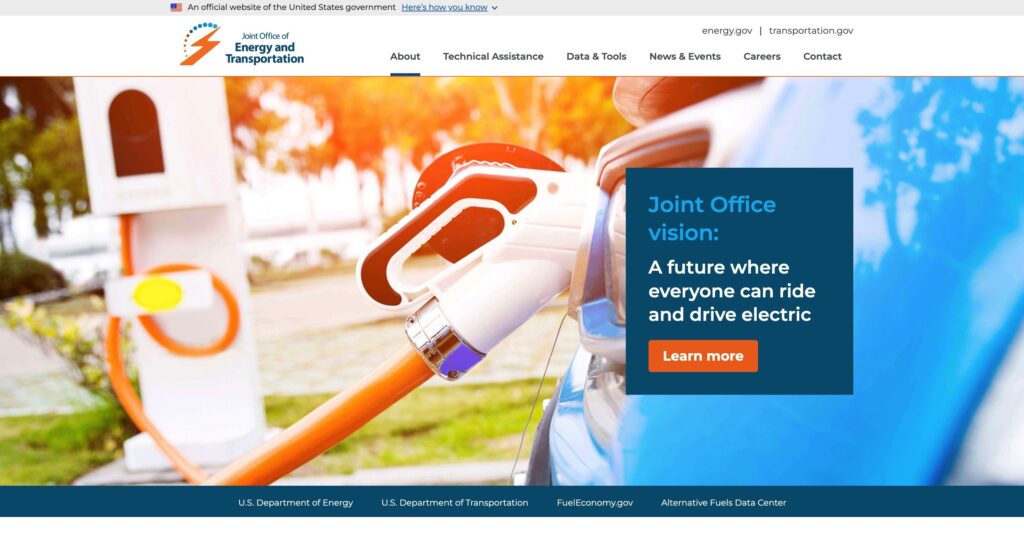
それでは、具体的な内容を一挙に紹介していきたいと思いますが、
まずはじめに、今回の合同事務所が発表してきた全国的な急速充電ネットワークにおいて設置される急速充電器というのは、
どのような電気自動車オーナーでも、しっかりと利便性を担保できるように、
1つの急速充電ステーションに、最低でも4台もの急速充電器を設置するということになりました。
したがって、例えば今後電気自動車の数が大幅に増えてきたという状況となっても、
その急速充電ステーションに到着すれば、必ず最低でも4台分の電気自動車を充電することができる充電器が設置されている、
つまり、充電待ちに遭遇するというリスクを大きく抑制することができる、
ということを意味するわけであり、
実際に我々日本市場においても、電気自動車のリーディングカンパニーであるテスラが、
独自に設置を進めているスーパーチャージャーに関しては、基本的には1つのスーパーチャージャーステーションに、4台という急速充電器を設置しているため、
充電待ちというリスクを大きく抑制することができています。

ただし、アメリカという国というのは、我々日本市場のような狭い国ではないわけであり、
特に大陸を横断するような場合では、そもそもの充電ステーションの数が全く足りなくなってしまうのではないかと心配されている方もいるとは思いますが、
今回の急速充電ネットワークのもう一つの大きな内容というのが、
各急速充電ステーションの間隔を、概ね80km程度とする方針を示してきている、
つまり、アメリカ大陸を横断する際でも、80km間隔で急速充電ステーションが設置、
しかもその上、その急速充電ステーションには、最低でも4台もの急速充電器が設置されている、
というようにイメージしていただければ、
とりあえずこの数年間という完全電気自動車時代への移行期間という過渡期的な意味合いにおいては、
非常に実用的な数の急速充電器が設置されていくという、
アメリカの電動化をさらに加速させる朗報となるのではないか、ということなのです。

しかしながら、その中でも最も懸念されてしまうポイントであると考えられるのが、
特に我々日本市場で設置されているような、いわゆる50kW級レベルの急速充電器だった場合、
充電にかかる時間が、想像以上にかかってしまい、
充電器の数は担保されたとしても、充電器のスペックが低い場合、
結果として、電気自動車における総合的な充電体験が改善されることは絶対にありません。

そして、今回連邦政府が表明してきた、今後設置していく急速充電器のスペックについてが、
最低でも150kW級の急速充電器である、ということであり、
それでは、この最低150kW級というスペックがどの程度のスペックを達成しているのかを理解していきたいわけでですが、
例えば、いよいよ今月である2月中から納車がスタートするとアナウンスされている、
日産のフラグシップクロスオーバーEVであるアリアの、
特に広大なアメリカ大陸を横断するために必須の、87kWhというロングレンジバッテリーを搭載したグレードで計算してみると、
そもそも日産アリアの急速充電性能は、最大で130kWという充電出力を許容することができるわけですから、
すでにこの時点においてでも、今回の連邦政府が設置を進めていく急速充電ステーションに向かえば、
毎回必ず、日産アリアの最大の充電性能を発揮することが可能となります。

そして、87kWhバッテリーを搭載している日産アリアに関しては、
すでに公式に、充電残量20%から80%まで充電するのにかかる時間が30分とアナウンスされていますので、
仮にマージンをとって、充電残量20%から80%の間のみを運用する、というような行程を組んだとしても、
高速道路を時速100kmでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値するEPAサイクルを基準にした航続距離が483km、
つまり、充電残量60%の航続距離は290km分ということになるわけですから、
例えば、満充電で出発して、途中400km程度走行した後に、概ね30分の充電時間を挟むと、
さらに290km先の充電ステーションまで、充電残量20%分を残して、余裕を持って走行することができますし、
そして何と言っても、今回の急速充電ステーションについては、
概ね80km間隔で設置が進められていくわけですから、
基本的には、次の充電ステーションで充電が必要になるまでに、
2-3箇所という充電ステーションを通過することになる、
よって、充電ステーションの多さによる安心感の醸成にも、大きく期待することができるのです。
日本とアメリカの充電インフラの性能の差がヤバイ、、
それでは逆に、我々日本市場において、2021年末に大黒パーキングエリアへの設置が完了し、
2022年以降、順次全国に設置を拡大していく予定の、
200kW級の急速充電器を例に当てはめて、日本市場の充電ネットワークと比較していきたいのですが、
まず結論から申し上げて、200kW級という数値というのはまやかしの数値であり、
一台当たりの最大出力というのは、最大でも90kWに制限されるということ、
さらに、アメリカ市場と明確に異なる制限というのが、
充電時間が一律一回30分に制限されてしまうという点、
しかもその上、その30分間の充電時間の全てで、90kW級という充電出力を発揮することはできず、
途中15分が経過した段階で、強制的に最大でも50kWという充電出力に制限されるという点、
さらにだめ押ししてしまえば、確かに合計して6台という急速充電器は併設されるものの、
後続車両が到着して充電をスタートした場合、先に充電していた車両の充電性能が制限されてしまい、
例えば3台目の電気自動車が充電をスタートすると、
最初に充電をスタートしていた電気自動車の充電許容出力は、
最大でも50kW程度にまで、留まってしまうのです。

したがって、この前提条件をベースにして、
日産アリアのロングレンジグレードで走行イメージを行ってみると、
充電時間30分という制限時間の中で充電できる電力量というのは、
最初の15分間で、90kWという充電出力を発揮できるものの、
日産アリアのシステム電圧は400Vですから、充電スタート時の充電残量20%程度の際は、概ね360V程度、
つまり、実際の充電出力というのは、概ね70kW前半まで上昇するはずですので、
おおよそ18kWh程度を回復見込み、
さらに、そのあとの15分間というのは、例外なく強制的に50kWに制限、
ただし400Vシステムのアリアについては、最大でも45kW程度がいいところでしょうから、
最大でも12kWh程度という電力量を回復見込み、
要するに、充電制限時間30分の間に充電することのできる電力量は、最大でも30kWhということになり、
こちらを最も信用に値するEPA航続距離に変換してみると、概ね167km程度、ということになります。

つまりどういうことなのかといえば、
2022年からアメリカ政府が補助金を交付して設置が進んでいく、最低150kW級の急速充電器を使用した場合、
概ね290km間隔で充電を30分行えばいいものの、
全く同じ車両を使用したとしても、
我々日本市場において、2022年から設置が進んでいく、なんちゃって200kW級の急速充電器を使用すると、
たったの160km程度という航続距離しか回復することができない、
しかも、アメリカ市場の場合、より休憩が必要であると感じれば、30分以上の充電を行っても良い、
したがって、一回の充電で400km近い充電を行うなんて運用方法も可能となるわけですが、
我々日本市場の場合は、基本的には一回30分という充電時間の制限がついてしまっていますので、
160km分の航続距離を回復してからは、充電をせずに移動できる行動範囲の上限が160kmに留まってしまう、
繰り返しとなりますが、
これは日産アリアのロングレンジグレードという、スペックが全く同じ電気自動車を使用しているのにも関わらず、
これほどまでに、運用方法が変わってきてしまう、
裏を返せば、電気自動車の利便性を担保する指標というのは、
その車両のスペックと同等、もしくはそれ以上に、
そのスペックを担保する充電インフラ側のスペックが重要であるということが、
図らずも浮き彫りとなってくるのではないでしょうか?
アメリカ国内の雇用創出をトッププライオリティに
ここまでは、アメリカの連邦政府が設置を進めていく急速充電ステーションの、大まかなスペックについてを、
特に日本市場において同時期に導入される急速充電ステーションのスペックと比較しながら、
その実用性についてを解説してきたわけですが、
そもそも今回設置が進められていく急速充電ステーションというのは、何も国営で運営されるということではなく、
あくまでも連邦政府が、充電器設置企業に補助金を交付することによって、
設置を加速してもらう、というものであり、
したがって、先ほどのスペックというのは、その補助金を交付するにあたって、最低限必要となる要件を示しているわけですが、
それでは、それ以外の、補助金交付に関する必須要件の中で、
特に特筆すべきポイントも紹介していきたいと思います。

まずは、その設置される急速充電器の製造を、アメリカ国内で製造されたものに限定して補助金を交付するという制限を設けてきたという点であり、
こちらについては、バイデン政権の掲げている政策理念である、アメリカ国内の雇用を創出するという理念を体現するためであり、
実際に、Tritiumというオーストラリアの充電器メーカーに関しては、
アメリカ国内で充電器を生産することを条件に、
今後の全米急速充電ネットワークに設置する急速充電器を提供することができますので、
今後世界有数の充電器メーカーたちの、
アメリカ国内に充電器を生産する工場を立ち上げるという流れが加速していくものと考えられます。

そして、今回最も重要視したい、
しかしながら、日本市場にとっての悲報とも言える制約というのが、
その設置されている急速充電器については、
北米市場で一般的に普及している、CCSタイプ1という充電規格を採用することが、補助金交付の条件となってしまったということであり、
実はこの充電規格に関しては、世界初の充電規格として、日本のチャデモ規格が北米市場においても展開されていたわけですが、
残念ながら、現状発売されている電気自動車において、そのチャデモ規格を採用している電気自動車というのは、
日産リーフただ1車種のみとなってしまい、
したがって、すでに北米最大の急速充電ネットワークを展開している、フォルクスワーゲングループ傘下のElectrify Americaに関しては、
2022年以降に設置する急速充電ステーションについては、
ごく一部の例外を除いて、原則的にはチャデモ規格の充電器を設置しない方針を決定した、
つまり、今後設置されるElectrify Americaの急速充電ステーションでは、
日産リーフを筆頭とするチャデモ規格を搭載した電気自動車は、
充電することができなくなってしまっていた、という状況だったのです。

そして、今回ついに連邦政府についても、
北米最大の公共の急速充電ネットワークであるElectrify Americaの決定の流れを踏襲して、
日本が世界に先駆けて展開したチャデモ規格を、金輪際採用しないことを決定してしまった、
はっきり申し上げてしまえば、
今回の決定によって、事実上チャデモ規格の死が決定してしまった、
日本発の充電規格の終焉が確定してしまった、ということになると思います。
チャデモ規格が負けた理由は、日本の怠惰です
ちなみにですが、
おそらく今回の連邦政府からの補助金を最も交付されながら、さらに設置計画を加速させていくであろう、そのElectrify Americaに関してですが、
こちらは現在アメリカの大陸全土に、最大350kW級という、超急速充電ステーションの設置を進めている状況であり、
このように、すでに大陸横断ルートを複数構築することができていますので、

あとは、その充電ステーションの間隔を、連邦政府の要請である、
概ね80km程度間隔へと縮めていけばいいだけ、という感じですし、
何と言ってもこのElectrify Americaについては、
350kW級という、アメリカ国内最速の充電ネットワークを構築しているわけですので、
それこそ、先ほど例として取り上げた、日産アリアを超える充電性能を有した電気自動車、
特に150kW級以上の充電出力を許容できる電気自動車についても、
しっかりと最大性を発揮できるよう対応可能でもありますから、
やはりこのElectrify Americaが、連邦政府からの強力な補助金をバックにして、
より安心して使用できる充電ネットワークを構築していくものと推測することができるでしょう。

このようにして、バイデン政権の大きな公約の柱でもあった、電気自動車用の急速充電ネットワークを構築するための、
大規模な補助金の概要についてを説明してきたわけですが、
やはり世界では、この150kW級という充電器のスペックが、今後の公共の急速充電性能のベンチマークとなっていくことが明らかとなったと思いますし、
それとともに、なぜアメリカ市場では、日本初の充電規格であるチャデモ規格を、ついに公に採用を見送るという決断をしてしまったのか、
それは、日本のチャデモ規格を採用した急速充電ステーションのスペックを比較していただければ一目瞭然、
ひとえに、電気自動車を利便性高く運用することのできるスペックを、
2022年になっても、世界を見渡しても今だにチャデモ規格のみが達成することができていないことが理由であり、
したがって、アメリカによる日本外しだー、などという意見というのは、極めてトンチンカン、
ただ単純に、日本の怠惰による実力不足によって、世界の急速充電規格レースから脱落してしまった、
ということですね。

何れにしても、アメリカについては、電気自動車戦争で中国に対抗するために、
国が主導して、大規模な充電インフラ整備のための補助金を投入することが決定したわけであり、
そして重要なポイントというのは、
我々日本市場にはびこる、20kW級急速充電器などという、
ユーザーガン無視の、利便性皆無な急速充電器などに補助金を適用せずに、
最低でも150kW級以上という、電気自動車ユーザーファーストな急速充電器に対してのみ、補助金を適用するという制限を設けてきたという点が、
我々日本市場の、ガバガバな補助金政策とは全く異なる、
金をつければいいという話ではないということが、図らずも浮き彫りとなってくる、ということですね。
From: Joint Office of Energy & Transportation、ARS Technica
Author: EVネイティブ

